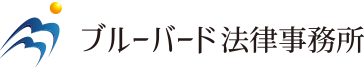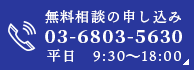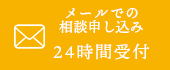遺留分の趣旨
亡くなった方(「被相続人」といいます)の意向を尊重するため、遺言書の内容はできるだけ実現されなければなりません。
しかしながら、例えば「愛人に対し、すべての財産を遺贈する」という遺言書が作成されていた場合、残された遺族の生活が危ぶまれるという事態も考えられます。
このようなあまりにも理不尽な事態を防ぐため、一定の範囲の相続人には、一定の割合の遺産を相続できることが法律上保証されています(民法1028条)。これは、亡くなった方が残した遺言書によっても侵すことのできないもので、「遺留分」と呼ばれています。
遺留分が認められる相続人とは?
相続人の範囲
まず、前提として、被相続人が遺言書を作成しないまま亡くなったとき、どの範囲の親族が相続人となるのか、民法上のルールを簡単にご説明します。
一つ目のルールは、配偶者(夫、妻)は必ず相続人になるということです。
そして、配偶者に加えて相続人となることができる親族は次のように順位が定められています。
- 子
- 直系尊属(父、母など)
- 兄弟姉妹
第2順位の者は第1順位の者がいない場合に限って、第3順位の者は第1・第2順位の者がいない場合に限って、相続人となります。これが二つ目のルールです。
以上のように、民法が定めた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人の相続分
民法は、法定相続人の範囲のみならず、法定相続人の取り分(相続分)も定めています。
相続分は、上記の相続順位に応じて次のように定められています。
- 配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合はさらに頭数で均等に分割します)
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・配偶者2/3、直系尊属1/3(父母がともに健在の場合は6分の1ずつになります)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数の場合はさらに頭数で均等に分割します)
なお、いずれのケースも、配偶者がいなければ他の相続人がすべての相続分を取得することになります。
遺留分が認められる相続人の範囲
では、遺留分はすべての法定相続人に認められているのかというとそうではありません。
遺留分が認められているのは、配偶者、子、直系尊属までで、上記第3順位の兄弟姉妹には認められていません。
これは、兄弟姉妹は配偶者や子などと比べると被相続人との関係が希薄で、遺族の生活の安定を図るという遺留分制度の趣旨が当てはまらないためです。
各法定相続人の遺留分の割合
冒頭で「一定の範囲の相続人には、一定の割合の遺産を相続できることが法律上保証されている」と説明しました。
「一定の範囲」についてはすでに説明したとおりですが、それでは「一定の割合」とはいくらなのでしょうか?
民法上は次のように定められています(同1028条)。
- 直系尊属のみが相続人の場合・・・1/3
- 上記以外の場合・・・1/2
直系尊属のみが相続人の場合は、その他の場合に比べ、割合が低くなっています。これも、直系尊属のみが相続人の場合は遺族の生活の安定という遺留分制度の趣旨がそれほど強くは当てはまらないためです。
また、注意しなければいけないのは、上記割合は法定相続人全体での遺留分の割合という点です(総体的遺留分)。各相続人の個別的な割合(個別的遺留分)に関しては、上述した各法定相続人の相続分に従って計算しなければなりません。
例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合はどうなるでしょうか。
この場合、総体的遺留分は上記のとおり1/2です。
そして、配偶者の相続割合は1/2、子の相続割合はそれぞれ1/4ずつであるため、
- 配偶者の個別的遺留分は1/4(=1/2×1/2)
- 子の個別的遺留分はそれぞれ1/8(=1/2×1/4)
ということになります。
同様に、法定相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者の相続割合が3分の2、父母の各相続割合が6分の1のため、
- 配偶者の個別的遺留分は1/3(=1/2×2/3)
- 父母の個別的遺留分はそれぞれ1/12(=1/2×1/6)
となります。
遺留分を侵害する遺言書は無効?
以上、一定の範囲の相続人には、遺言書によっても侵すことのできない遺留分という権利があることを簡単にご説明しました。
それでは、遺留分を侵害するような遺言書は無効となってしまうのでしょうか?
遺言によって遺留分を侵害することが許されないのであれば、そのような遺言は当然に無効となってしまうかのように思えるかもしれませんが、実はそうではありません。
遺留分を侵害する内容の遺言も有効ですし、現実においても、遺留分を侵害された内容の遺言書に沿って遺産の帰属が決められてしまうことが多々あります。
逆に言えば、法定相続人が遺留分を請求するには、自ら侵害者に対し、積極的に遺留分の主張をしていかなければならないのです。
次回の記事では、遺留分を主張するための方法、期間制限など、遺留分侵害額の請求に関し注意すべき事項について説明したいと思います。